奇妙なままでいてほしかった。実写映画『秒速5センチメートル』が「浄化」したもの
撮影:筆者
新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』(2007)の実写映画が、10月10日に公開された。
本作は、写真家・映像作家として活躍する奥山由之監督にとって初の大型長編商業映画監督作である。主演を務めるのは松村北斗と高畑充希。ここでは、原作アニメーションを愛し、舞台となった新宿の街に特別な思いを持つ編集部スタッフが、実写版を見て綴ったエッセイをお届けする。筆者が撮り続けてきた新宿のフィルム写真を織り交ぜながら、原作の持つ「奇妙さ」、実写映画が失ったもの、そして映画表現の未来について問いかける。
*本記事は、映画の内容に関わる記述を含みます。ネタバレを気にする読者の方は、映画の鑑賞後にお読みになられることをおすすめします。

「奇妙さ」の美学
2007年に公開された新海誠監督のアニメーション映画『秒速5センチメートル』は、極めて奇妙な作品である。過去という亡霊に取り憑かれた主人公・遠野貴樹が、ぞっとするようなセリフを呟きながら、小学校で出会った篠原明里への捨てきれない思いを30代まで持ち越し、新宿を彷徨いながら病んでいく物語である。新海監督自身も初期作品の奇妙さを自覚していたのか(*1)、あるいは本作への批判を受けてのことか、公開後はノベライズ化、マンガ化が次々と行われ、原作の抽象性は徐々に削ぎ落とされていった。そして最後の戸締りとなったのが、奥山由之監督が手がける2025年の実写化である。
新海監督の原作は、膨大なクライマックスシーンを持たない3部構成の作品だ。観る者は、貴樹と明里の出会いと栃木への旅路を描く「桜花抄」から、鹿児島県の種子島に移り住んだ貴樹と、彼に密かな恋心を寄せる澄田花苗の物語を追う「コスモナウト」、そして成人した貴樹の生活を描く「秒速5センチメートル」へと引き込まれていく。それらはすべて、主に主人公の闇に満ちたナレーションとともに展開される。そして貴樹の声を担当する水橋研二の演技がまた素晴らしい。身体の内側から吐き気が這い上がってくるような、絶妙な不気味さを湛えているのだ。

貴樹の「奇妙さ」は第1話から滲み出ている。「僕と明里は精神的にどこか似ていたと思う」「手紙から想像する明里はなぜかいつもひとりだった」。明里というキャラクターが確かに存在しているかのように見えて、実際には貴樹の解釈に呑み込まれてしまい、性格も素顔もよく見えない女性として描かれている。さらに貴樹の言葉は、13歳の少年が口にするようなものではない。過去を反芻するメランコリックな大人の、後悔に染まったモノローグなのだ。

物語は第2話へと進む。初恋を忘れられないまま、拒絶を恐れるかのように行動も起こさない貴樹と、そんな彼に恋心を抱き始める種子島の女子高校生・澄田花苗が主人公となる。ここで新たに、澄田のピュアな視点がナレーションとして加わる。
彼女の目には、クラスメイトと普通に会話している貴樹が、どこか遠くて、奥深い存在に映ってしまう。それは恋した相手への期待と、自分の妄想が細やかに重なり合っていく過程なのだろう。しかし澄田の純粋な言葉とは対照的に、貴樹がナレーションするシーンはすべてメランコリーに満ちている。何気ない日常が悲観的に歪められ、観る者を確実に貴樹の心の闇へと吸い込まれていく。彼は自分の妄想を遥か遠い宇宙に重ね、無限の可能性の前で明里といる幻想を見続ける。行動を起こすことなく、ただひたすらにその思いを自分の内側に詰め込み続けるのだ。

遠野貴樹の闇を返してよ
さて、原作の話はここで一旦切り上げたい。なぜならこれほど抽象度の高い作品だからこそ、その解釈と受け止め方は、きっとそれぞれの世界観と経験に委ねられているからだ。これは批評から逃げるための言い訳ではなく、抽象性を積極的に受け止める褒め言葉である。あの作品はやはり私にとって特別だった。あの作品を私は奇妙と認識しながらも、共感せざるを得なかった。遠野貴樹という男は、まるで人間との付き合いが上手くいかない私の分身のようにも見えていた。
実写版の予告編を初めて目にしたとき、真っ先に思ったことは、松村北斗の「遠野貴樹」は闇を知らない男だということだった。その声には確かに悲しみが滲んでいたとしても、人に一方的に執着する、あの病的な響きがなかったのだ。しかし目の前に映し出されるヴィジュアルは、紛れもなく『秒速5センチメートル』だった。奥山監督だからこそ、奥山監督でなければ成り立たなかった原作の世界がそこには広がっていた。その後、私は胸が痛むほど美しい映画を劇場で観た。そして同時に、強く絶望したのだった。

原作を彷彿とさせるあわい描写、忠実に再現されたカット、ノスタルジックなフィルムの質感——原作が好きだった私が嫌いになる要素などひとつもないはずなのに、心と身体に強い拒否反応が生じていた。なぜなのか。それはヴィジュアルが美しくはあったが、実写版が驚くほど単純で、重みを持たない物語だったからだ。そして何より、遠野貴樹の「浄化」があまりにも不自然だったからだ。

実写版の貴樹は、自分に自信を持てず、生きる喜びをどこかで見失ってしまったアラサーの男として描かれる。明里への執着心は子供の頃の夢とふたりの約束という美化された記憶に塗り替えられ、ちゃんとした大人になれなかった自分への苛立ちに焦点が当てられる。誠実で、切実な人。そう言われる貴樹に、上司、科学館の館長、高校教師、元カノといったサイドキャラクター、そして最後には明里本人が「救い」の手を差し伸べる。そして貴樹は自分を取り戻し、プラネタリウムで「天職」に就いてこれからの人生を歩んでいくのだった。こうしたハッピーエンドは綺麗事に過ぎず、果てしなく空虚である。
また、高畑充希が演じる「篠原明里」ほど、不自然に空を見上げる人がいるだろうか。実写版で明里は、新宿紀伊國屋という職場、同僚、友人、夢や希望を持つ中身のある理想の女性として生まれ変わる。「あの子はずっと上を向いていただろう」といった、彼女の生き様まで規定する演出まで施されていた。明里が具体化されるたびに、観客が想像する余白は容赦なく奪われていく。原作にはなかったふたりのつながりも新たに生み出され、貴樹の奇妙な執着は浄化され、ありふれた切ない初恋物語へと堕してしまったのだ。

記憶に残らない美しさ
「アニメ」の表現をしばしば痛々しく感じることがある。現実と非現実の境界を横断するこの表現方法は、通常は口にしないようなセリフを許容する。また、そこで描かれる風景は現実を参照し、模倣しながらも、制作者のレンズを通して拡張されていく。
新海監督が描き出す新宿は私の心をしっかりと掴んでいた。2008年に来日して、リムジンバスから初めて降り立った新宿駅西口。いつも行く映画館、ふらっと立ち寄る本屋、フィルムを現像するカメラ屋——あの日以来、私は新宿の街を隅々まで歩き、いまもここは私の生活の拠点である。しかし何度も西新宿の高層ビルにカメラを向けても、自分の目に映っていた美しさを再現することはできなかった。ヴィジュアル以外に、その風景には私の想いもたくさん詰まっていたからだろう。

実写版『秒速5センチメートル』は最初から最後まで美しかった。新海監督へのオマージュとしても、奥山監督の世界観の表現としても。しかし、ふと考えてみれば、先日2回目の試写会に行ったばかりなのに、あの美しいショットがひとつも記憶に残っていない。それぞれが「映えていた」のに、意味を持たなかった。Instagramで気に入った写真をブックマークし忘れたかのように、一瞬でこの映画を見失ってしまったのだ。
ここに、静止したアニメーションと動き続ける映像との、決定的な違いがある。限られた部分しか動かないアニメーションでは、カットの切り替わりこそが躍動感を生み出し、物語を前進させる原動力となる。ところが映像では、この原理は通用しない。止まっているように見える瞬間においても時が流れ、俳優の演技、カメラワーク、音響、脚本が共鳴し合うからこそテンションが生まれる。しかし、奥山監督はノスタルジーに浸った美しい瞬間を切り取ることには長けているが、その映像に物語としての意味を宿すことができていない印象を受けた。結果として、映画に「間(ま)」が生まれることなく、俳優の演技は映像美に呑み込まれてしまい、息つく暇もないカット割りは各シーンの緊張感を容赦なく殺していく。さらに、新たなキャラクターや設定という「説明」が次々と追加され、原作が持っていた抽象性は埋め立てられてしまった。
ありあふれたCMやMV(ミュージックビデオ)を思わせるカット。文字情報を挿入する余白を残して顔に寄せられたカメラ。どこかで見たことのある安易な構図。映像に合わせられたありきたりの楽曲。そして隙間を埋めるように差し込まれるセリフ——この映画は最初から最後まで、ヴィジュアルで物語を語りたいのか、それとも俳優の演技で語りたいのか、決めかねていた。そのためひとつのシーンに熱意と感情が積もることもなく、ぎこちない断片が続き、ただ2時間が過ぎていった。ほら、このショット美しいだろう? まるで観客に腕前を見せつけるかのように。「美しいもの探し」——そういう映画だった。

繊細かつ特徴的な映像美で知られるカナダ出身のグザヴィエ・ドラン監督が、商業映画について問われたインタビューでこう語っている。「映画をインディペンデントとコマーシャルというふたつのカテゴリーに分けたりはしない。私にとって良い映画と悪い映画があるだけだ。そして良い映画とは、ストーリーやテーマ、使命に忠実なものだ」(*2)。そして、2019年に最後の長編映画を制作したドラン監督は、34歳で引退してしまう。時間と熱意を注いでも、商業的ではない映画は見られなくなったからだ、という。映画を価値づけるのはハッピーエンドなのだろうか。それとも、その映画が果たそうとしている使命だろうか。実写版『秒速5センチメートル』を劇場で眺めながら私はどこかで映画の未来を悲しく思えるようになった。

闇への共感、浄化への拒絶
「ただ生活をしているだけで、悲しみはそこここに積もる。日に干したシーツにも、洗面所の歯ブラシにも、携帯電話の履歴にも」(アニメーション版『秒速5センチメートル』より)
このセリフを初めて聞いたとき、私は初めて架空のキャラクターに心の底から共感した。そして何度もその瞬間を体験してきた。将来に不安を抱く貴樹のように、私も新宿の高層ビルの谷間で自分を見失っていた。あるいは過食症で食べ過ぎた後の瞬間。部屋中に散らばるプラスチック袋とコンビニ商品の包装。そこには確かに悲しみ、怒り、無力感、自分を嫌悪する気持ちが積もっていた。過食の嵐が過ぎ去った後、部屋も身体も静まり返り、ホコリが落ちてくる音さえ聞こえる。その瞬間は写真のように動かないが、どこまでも美しい。動いてしまえば自分が変わってしまうことを恐れるように、私は自分の周りに悲しみを積もらせていた。
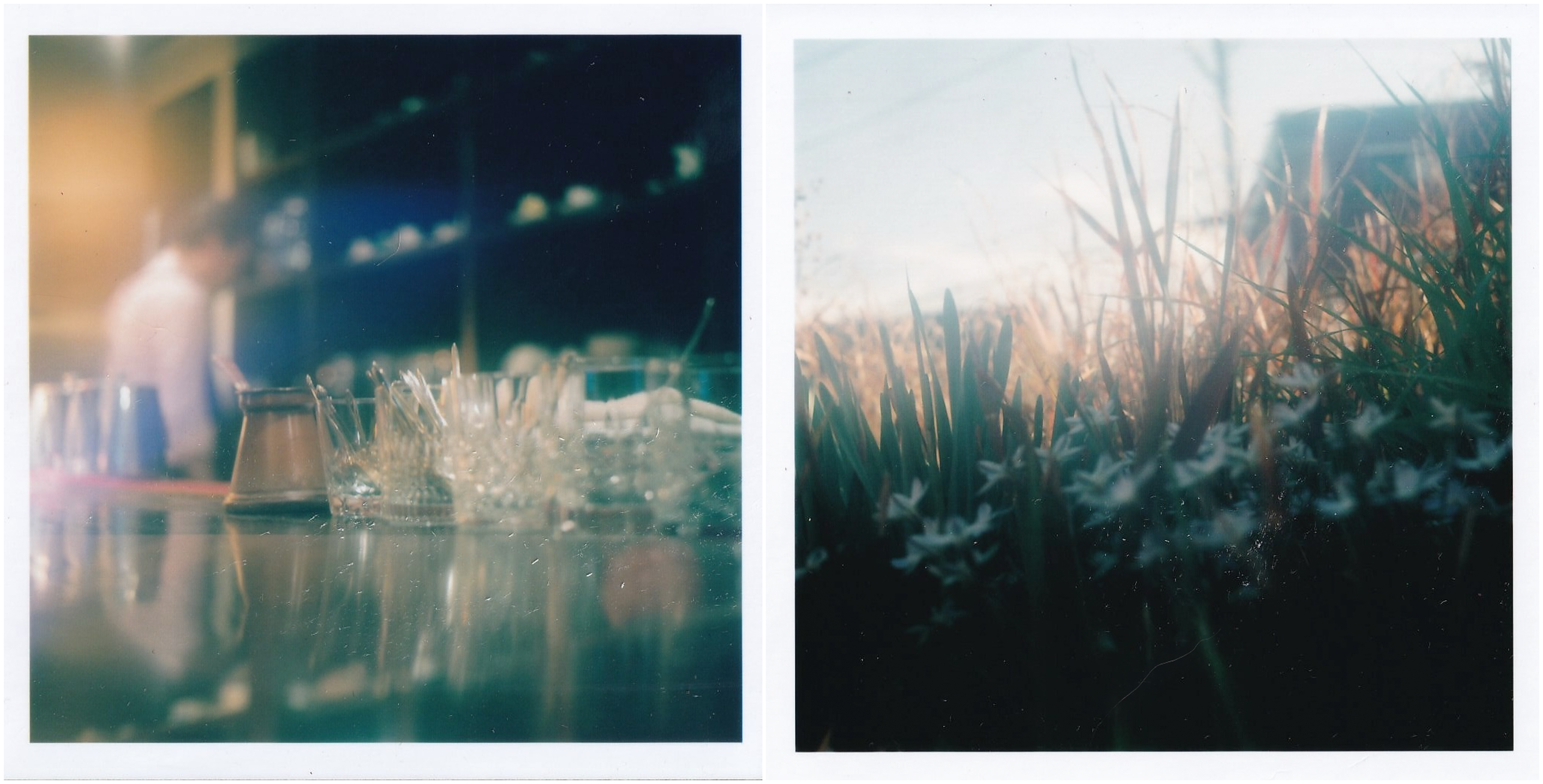
誠実なんだから彼に共感してよ、と観客に訴えかける実写版。しかし私は「善良な青年」としての貴樹ではなく、心に染み込んだ闇と気持ち悪さに共感したかった。悲観的に生き続ける主人公のままでいてほしかった。誰かを愛するということは、その人に執着すること、依存することも意味するかもしれない。心に闇があるからこそ、綺麗な夕日を見ながら素直に涙を流せるのかもしれない。悟りも救いも訪れないまま人生が流れていくことだってある。ハッピーエンドで終わらない映画を作ってもいいのだ。だから恐れずに、奇妙な貴樹を奇妙なままで描いてほしかった。
しかし、実写映画『秒速5センチメートル』で浄化され、無害化された遠野貴樹はもはや別人だった。それは確かにひとつの"いまどき"の物語として存在し続けるだろう。観客の嗜好に迎合し、映像を極限まで美しく磨き上げた——それ以上でもそれ以下でもない、そういう映画だった。

*Tokyo Art Beatでは、新海誠についての論考も収録した著書『「世界の終わり」を紡ぐあなたへ―デジタルテクノロジーと「切なさ」の編集術』などで知られる北出栞によるレビューも公開中。
*1—— 「松村北斗 × 奥山由之 × 新海誠 スペシャルトークセッション 【PART 1】」(2025年9月26日公開、https://www.youtube.com/watch?v=0rAEA0WW5mk)
*2——"Cannes Winner Xavier Dolan Talks Adele and Movies Without Happy Endings"(2016年5月25日公開、https://www.youtube.com/watch?v=HbAH3XzRRRc)
灰咲光那(編集部)
灰咲光那(編集部)



